9月5日 金曜 19:00 からフジテレビの『坂上どうぶつ王国』で『咬みつき犬』の更生についての放送があります。
わたしも以前から、手の付けられないペットのしつけについては、興味があり、今回は凶暴な『咬みつき犬』の更生ということなので、番組の放送を前に、『咬みつき犬』について、どのような背景や問題があるのかを調べてみました。
放送を見る前でも、見た後でも、この記事を読むと『咬みつき犬』についての考えが深まると思います。
是非最後までお付き合いください。
『咬みつき犬』とは
これは、他人に咬みついて傷を負わせたことのある犬を指すことが多いです。
そのような犬は、場合によっては危険な犬として扱われ、自治体への登録や特別な飼育方法が義務付けられることがあります。
例えば、特定犬種として指定され、檻の中での飼育や、外出時の口輪の着用などが義務化される場合があります。
病院もですが、保健所案件です( ̄▽ ̄;)
— おんそくまる@柱島提督@青TL50 (@__T_owl) May 6, 2024
噛んだ犬の所有者、すなわち飼い主は所轄の保健所に咬傷届を提出しなければなりません
東京都の条例を例に挙げますが、どの自治体にも同様の条例がありますhttps://t.co/TwQ0mTKiz2
しかし、単に攻撃的な犬として片づけられるだけでなく、問題行動の背景にはさまざまな理由があると考えられています。
過去の虐待やトラウマ、適切な社会化の欠如、病気や痛みなどが原因となっていることも少なくありません。
そのため、安易な殺処分を避けるため、専門家による行動修正やリハビリテーションが行われることも増えています。
『咬みつき犬』の問題とは
最も深刻な問題は、人や他の動物に怪我を負わせてしまうことです。
以前、東京の代々木公園のドッグランで
— タンタンパパ (@tintinpapa1) December 2, 2023
こんな大惨事が起きました…
ボーダーコリーとサモエドの咬傷事件です。
皆さんは愛犬をドッグランに連れて行ってますか?
ドッグランは犬にとって実に楽しい場所ではあるでしょうが、
同時に恐ろしく危険な場所でもあります↓https://t.co/BKX9MJ7b6K
咬傷事故は、被害者に身体的な痛みや精神的なトラウマを与えるだけでなく、最悪の場合、命を奪うことさえあります。
また、咬傷事故を起こした犬は、飼い主が責任を問われたり、自治体から厳しい処分を課せられたりする可能性があり、犬自身も殺処分されるリスクを抱えることになります。
【漫画】ノーリードの大型犬に噛まれた!「犬を殺処分したら…あなたを許さない」加害者も犬も被害者もつらい「犬の咬傷事故」の実態 #SmartNews
— 楽座 (@biburiomaniarak) May 19, 2024
読んでて涙が出てきた…わしは絶対こんな大人な対応は出来ん…少なくともこの爺は半殺しにするし噛んだ犬は悲鳴あげるまで殴る https://t.co/KnU2JRU4qT
さらに、問題行動が原因で散歩や外出が困難になり、犬の生活の質が低下し、飼い主も精神的な負担を抱え、孤立してしまうことも少なくありません。
『咬みつき犬』の更生
まず、なぜその犬が咬みつくのか、その根本原因を特定することが重要です。
恐怖、縄張り意識、痛み、過去のトラウマなど、さまざまな要因が考えられます。
原因が特定できたら、それに応じた行動修正プログラムが組まれます。
具体的には、犬に安全な環境を提供し、ストレスを軽減させること、ポジティブ・リインフォースメント(ご褒美を与えることで良い行動を促す方法)を用いたトレーニングを行うこと、そして徐々に社会化を進めていくことが挙げられます。
また、必要に応じて、専門のドッグトレーナーや獣医師、動物行動学者などと協力し、『咬みつき犬』の更生にあたります。
来週9/5(金)の坂上どうぶつ王国に焼津市で活動している「わんずふりー」さんが出演します。保護犬は世間に認知されてきたけど、「咬傷犬」の保護についてはまだまだ知られていません。犬に興味がある方はぜひ見てほしいです。齋藤さんの人柄が素敵です。あれはもしや「のぶ」では?#わんずふりー pic.twitter.com/ensnldt4eA
— キラリン (@MYFC_Direct) August 30, 2025
『咬みつき犬』になりやすい犬種はいるのか
- チワワなどの小型犬
- 体が小さいため恐怖心から威嚇行動を取りやすく、咬みつく傾向があるといわれています。
また、その可愛らしさから、過保護に育てられ、問題行動を助長してしまうケースも見られます。
- 体が小さいため恐怖心から威嚇行動を取りやすく、咬みつく傾向があるといわれています。
- ジャーマン・シェパードやドーベルマンなどの大型犬・警備犬
- 元々、番犬や警備犬として使役されてきた犬種で、縄張り意識や警戒心が強く、適切なトレーニングを怠ると攻撃的になりやすいといわれています。
- ピット・ブルなどの闘犬種
- 闘犬として使役されてきた歴史があるため、強い攻撃性を持ち、一度咬みつくとなかなか離さない傾向があるといわれています。
『咬みつき犬』に育てないためには
では、咬みつき犬に育てない為には、どうしたらよいのでしょうか?
- 子犬の頃からの社会化
- 生後3ヶ月頃までに、様々な人や犬、環境に触れさせることで、外部の刺激に慣れさせ、恐怖心や警戒心を軽減させることができます。
- ポジティブ・リインフォースメントを基本としたトレーニング
- 犬が良い行動をした時に褒めたり、おやつを与えたりすることで、学習を促し、信頼関係を築くことができます。
叱りつけるような方法は、犬を怯えさせ、信頼関係を壊してしまう可能性があります。
- 犬が良い行動をした時に褒めたり、おやつを与えたりすることで、学習を促し、信頼関係を築くことができます。
- 犬のボディランゲージを理解する
- 犬がストレスや不安を感じているサイン(あくび、目をそらす、耳を後ろに倒すなど)を読み取り、早めに対処することで、咬みつきなどの問題行動を未然に防ぐことができます。
- 適切な運動と精神的な刺激
- 犬種に応じた十分な運動や、知育玩具などを使った遊びを通して、犬のエネルギーを発散させ、ストレスを溜めないようにすることが重要です。
まとめ
『咬みつき犬』の問題は、犬種や個体差だけでなく、飼育環境や飼い主との関係、社会化の度合いなど、様々な要因が複雑に絡み合って起こるものです。
安易に「凶暴な犬」とレッテルを貼るのではなく、その背景にある理由を理解し、専門家と協力しながら、根気強く更生に取り組むことが重要だと改めて感じました。
今回の『坂上どうぶつ王国』の放送をきっかけに、多くの人が『咬みつき犬』の問題について理解を深め、より良い共生社会を目指すきっかけになればと願っています。
参考
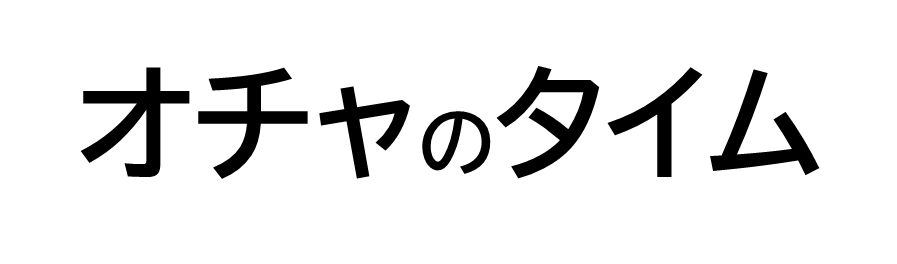


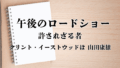
『咬みつき犬』とは、一般的に『咬傷犬(こうしょうけん)』と呼ばれます。